遊々亭攻略ブログ
遊戯王 OCG 遊々亭Blogです。
遊々亭一押しのプレイヤーさん達による攻略情報やゲームに関する様々な情報、担当のおすすめなど、遊戯王 OCGに関する情報を配信していきます。 Twitterでも情報配信中です!
posted 2020.01.30

こんにちは、遊々亭@遊戯王担当です。
本日は超強化買取中カードをテーマ別にご紹介致します!
今回ピックアップしているカード以外の関連カードも買取しておりますので、気になるカードは[買取]タブから要チェックです!
| オルターガイスト関連 | |
 | |
| 超 強化買取中! <URオルターガイスト・メモリーガント> <SEオルターガイスト・メモリーガント> | |
| 超 強化買取中! <URオルターガイスト・プークエリ> <SEオルターガイスト・プークエリ> | |
| 超 強化買取中! <SEオルターガイスト・マリオネッター> | |
| 超 強化買取中! <ULオルターガイスト・プライムバンシー> <SEオルターガイスト・プライムバンシー> | |
| 霊使い関連 | |
 | |
| 超 強化買取中! <20thSE灼熱の火霊使いヒータ> <20thSE蒼翠の風霊使いウィン> <20thSE清冽の水霊使いエリア> | |
| 超 強化買取中! <SE水霊使いエリア> <SE火霊使いヒータ> <SE風霊使いウィン> <N地霊使いアウス> <N風霊使いウィン> <N水霊使いエリア> <N火霊使いヒータ> | |
| 超 強化買取中! <N憑依装着-アウス> <N憑依装着-エリア> <N憑依装着-ヒータ> <N憑依装着-ウィン> <NR憑依装着-ライナ> | |
| 超 強化買取中! <SE憑依覚醒> <SR憑依覚醒> | |
| 銀河眼関連 | |
 | |
| 超 強化買取中! <20thSE銀河眼の煌星竜> <SE銀河眼の煌星竜> <UL銀河眼の煌星竜> <UR銀河眼の煌星竜> | |
| 超 強化買取中! <UR銀河眼の光波刃竜> | |
| 超 強化買取中! <SRCNo.107 超銀河眼の時空龍> <URCNo.107 超銀河眼の時空龍> <ULCNo.107 超銀河眼の時空龍> <URNo.107 銀河眼の時空竜> <ULNo.107 銀河眼の時空竜> | |
| 超 強化買取中! <URNo.90 銀河眼の光子卿> <CRNo.90 銀河眼の光子卿> | |
上記以外のカードも随時買取募集しております!
気になるカードは商品ページの[買取]タブからカード名を入力するか、 超!強化買取ページや買取強化ページにてご確認ください!
今回の買取強化情報は以上です。
それでは( ̄ー ̄)ノ
遊々亭公式Twitter、担当Twitterでは、更新情報や、Twitter限定のお買い得情報等々、リアルタイムに情報を発信しています!
【遊々亭 公式Twitter】 @yuyutei_news
【遊々亭 遊戯王OCG担当Twitter】 @yuyutei_yugioh
posted 2020.01.27
Byオオニシ

ETERNITY CODE編
1月11日に発売した「ETERNITY CODE」のカードからブロガーさん達に注目のカードをピックアップしてもらい、各カードについてコメントを頂きました!
今回はオオニシさんに頂いたレビューを公開していきます!
こんにちは。初めての方は初めまして、オオニシと申します。 今回は1月11日に発売した「ETERNITY CODE」のレビューということで、個人的に「オッ!」と思ったカードをピックアップしてみました。これを読んで、一緒に「オッ!」と唸ってみませんか?
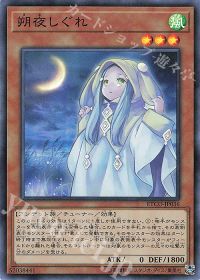

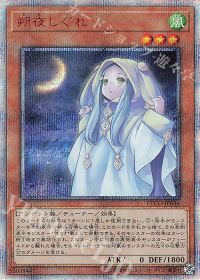
効果自体は<ヴェーラー><泡影>ですが、発動タイミングが特殊召喚時に限定されています。これだけ見れば「ヴェーラーで良いのでは?」と思われますが、逆に言えば「自分のターン中」かつ「場の状況に関わらず」発動することができます。
更に、対象のモンスターが場を離れると攻撃力分のダメージを与えられる効果も付随しているため、ライフカットが遅いデッキや「打点は出せるが瞬間的に8000を出すのは苦手」といったデッキで採用すれば、キルラインを大幅に下げられる使い方が可能です。
手札誘発はその大抵が「状況に応じた効果(万能な妨害効果は無い)」で、対戦相手や環境によって使い勝手は大きく変わります。なので、今回登場した「朔夜しぐれ」も採用タイミングを見極めたいところです。逆に採用率が高くない点を逆手にとって採用し、<抹殺の指名者>等で撃ち落とされない戦略もアリですよね。

類似効果として<トラップ・イーター>が存在しますが、あちらはチェーンを組まず「壊獣」同様に表側罠を処理できます。ただし罠のみで、今回の「マジカル・ハウンド」は魔法カードも処理できるという優位点があります。そしてチューナー。もう「強そう」ですよね。
表側の魔法カードというと<バベル><里>などの制圧札が挙げられ、PゾーンのPカードも含まれます。それらをバウンスした上で「手札・墓地」から出てこれるのは汎用性が高いといえます。
しかしながら、チェーンを組む特性上「その<センサー万別>を対象にマジカルハウンド発動!」「いや<妖魔>で」と止められる可能性は大いにあり、強烈な永続罠を潰す用途ならば「トラップ・イーター」にはやはり劣ります。
差別化として「レベル1」「通常召喚可能」「魔法も戻せる」「チューナー(<ハリ>から出せる)」点を生かし、採用を検討したいものです。

こちらは所謂「汎用カード」では無いのですが、ピックアップした理由として【召喚獣】での利用方法が「すげ!」と興奮したからです。
何がすげぇかというと、普通に<暴走魔法陣>の発動下で<召喚魔術>→「アウゴエイデス」を出して(1)の効果を使用すると、暴走魔法陣の「融合召喚時に相手は何も使えないよ」効果により、実質チェーン不可の除去となる。
「すげ!」と思ったのはコレであり、別に自分は【召喚獣】を使用している訳でも無いのですが、この興奮を伝えたいがためのピックアップでした。あとは(2)の効果により、初の「単体で瞬間火力が4000を超える召喚獣」なので、ガラ空き相手にライフを取りやすくなりました。
以上、オオニシさんのETERNITY CODEレビューでした。
オオニシさん、ありがとうございました!
posted 2020.01.24
こんにちは、遊々亭@遊戯王OCG担当です!
今回は現時点で2020年1月に売れたカードをランキング形式でまとめました!
それではどうぞ!
販売ランキングTOP3
 | 第3位 |
|---|---|
| <R宵星の騎士ギルス> | |
効果 |
第3位は宵星の騎士ギルス!
オルフェゴールで重宝される墓地肥やしに加え、自身のみで2枚分のリンク素材になれるトークン生成効果でオルフェゴールというテーマの安定感を劇的に向上させました。
(1)の効果が特殊召喚にも対応していてオルフェゴール+星遺物と効果範囲が広く、トークン生成効果はテーマに関わらず使うことが出来る事からギルス+展開パーツで様々なデッキに組み込む事も可能です。
機械族・闇属性かつ守備力0とサポートが豊富なステータスである点も見逃せません!
 | 第2位 |
|---|---|
| <SR融合派兵> | |
LINK-2 |
第2位は融合派兵!
このカード自身をデッキに投入している融合素材となるカードの延長として用いる感覚でしょうか。
素材指定が曖昧な<アブソルートZero>等を指定することが出来ず、融合モンスターしかEXデッキから出せなくなる縛りがありますが、融合を繰り返すデッキの素材モンスターにアクセスしておく事ができ、複数の融合素材を投入しているデッキでは状況に応じて出す融合モンスター(の融合素材)を選ぶ事ができます。
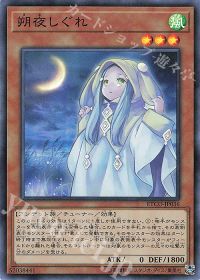 | 第1位 |
|---|---|
| <SR朔夜しぐれ> | |
効果 |
第1位は朔夜しぐれ!
出ました。新たな手札誘発です!
相手がモンスターを特殊召喚した場合というタイミングの指定はあるものの、相手の展開パーツに対する妨害の役割は元より、<ファンタズメイ>や<宇迦之御魂稲荷>等の、特殊召喚に加えてなんらかの効果を発動するモンスターを止めたうえでライフポイントを奪いにいけるという貫通札としての側面も見受けられます。
モンスター効果の無効という点で一部のカードと役割が被りますが、効果範囲の違いやそれぞれのメリット・デメリットを鑑みてデッキに合ったものを選択していくとよいでしょう。単純にたくさん積めるようにもなりました。
今回の販売ランキングは以上になります。
ではまたヾ( ´ー`)ノ
遊々亭公式Twitter、担当Twitterでは、更新情報や、Twitter限定のお買い得情報等々、リアルタイムに情報を発信しています!
【遊々亭 公式Twitter】 @yuyutei_news
【遊々亭 遊戯王OCG担当Twitter】 @yuyutei_yugioh



































