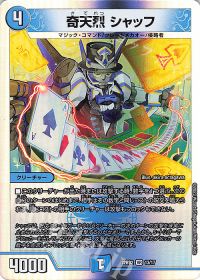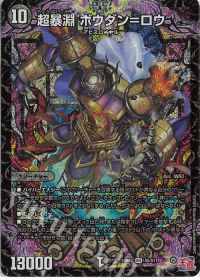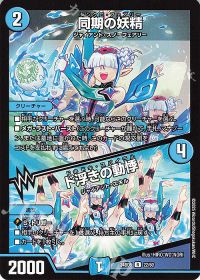遊々亭攻略ブログ
デュエルマスターズ 遊々亭Blogです。
遊々亭一押しのプレイヤーさん達による攻略情報やゲームに関する様々な情報、担当のおすすめなど、デュエルマスターズに関する情報を配信していきます。 Twitterでも情報配信中です!
【デッキ紹介】青黒コンプ
posted 2025.11.27
Byyoku

【デッキ紹介】青黒コンプ
今回は10月に行われたDMGP2025-2ndのday2オリジナルに参加してきましたので、実際に使用したデッキのご紹介をします。
私がGPオリジナルで使用したデッキは「青黒コンプ」です。「青単サイバー」や「闇王ゼーロ」、「デアリバイク」など他にも強力なデッキがある中でどのようにして「青黒コンプ」を使うことになったのか、各カード採用理由などを解説できたらなと思っております。
それでは、GP2025-2ndの環境考察から振り返っていこうと思います。
環境考察とデッキ選択
まずは、GPのオリジナル環境による環境考察です。GP前の環境トップは「青単サイバー」「闇王ゼーロ」「デアリバイク」「ドリームメイト」などが活躍しており、この中でも特に「青単サイバー」が頭一つ抜けて強く、GPでの使用者も最も多いであろうと予想していました。
そして次に注目していたのが、赤抜きの「4Cゼーロ」や「ドロマーゼーロ」です。突如として環境入りしたことでまだプレイヤー間でのデッキに対しての理解が追い付いていなかったり、デッキ構築にかなり自由がある為、人によって採用しているカードが違うことで初見殺しができるので、各チーム毎に調整された様々な「闇王ゼーロ」デッキと対面することになるのではないかなと考えていました。
そして、自分が使用するデッキについてです。大会直前までは「青単サイバー」を使用する予定だったのですが、全てのプレイヤーが間違いなく「青単サイバー」を意識したデッキを持ち込んでくること、どの相手も「青単サイバー」対面をしっかりと練習した上でGPに参加してくることを考慮すると、強いデッキであることは間違いないが通りが良い環境ではないなと判断したので「青単サイバー」以外のデッキを模索することにしました。
「青黒コンプ」を選択した理由
自分の中で特に意識したのが「青単サイバー」と「闇王ゼーロ」2つです。この2つに対してアプローチできるデッキかつ、十分な受け札を採用できるデッキは何だろうと考えた時に思いついたのが「青黒コンプ」でした。「青黒コンプ」の主張点は主に3つあります。
1つ目はハンデスです。「青単サイバー」と「闇王ゼーロ」はどちらも手札にパーツをそろえて一気に行動を開始するデッキなので、ハンデスでキーパーツを抜くことでかなり時間を稼ぐことができるのではないかなと考えました。
この他にも「デアリバイク」や「トリーヴァバンデ」のようなデッキは手札リソースがかなり細いデッキタイプになるので、環境全体としてハンデスの通りが良いのではないかなと考えました。
2つ目は優秀なメタクリーチャーを採用できることです。
<異端流し オニカマス>で<昇カオスマントラ>で出てきたクリーチャーや<DARK MEMORY CONTAINER>を手札に返すことができ、<ボン・キゴマイム|やせ蛙 ラッキーナンバー ここにあり>で出たばかりの<愛銀河マーキュリー・スターフォージ>を止めることができます。そして、<奇天烈 シャッフ>で5を宣言して<愛銀河マーキュリー・スターフォージ>をもう1ターン止めたり、8を宣言して<闇王ゼーロ>を止めることができます。
そして、それぞれに対して有効なメタカードを駆使して相手の動きを遅らせながらこちらの盤面を広げていき、<奇天烈 シャッフ>や<飛翔龍 5000VT>でロックを掛けながらビートして勝ちに行くという寸法です。 3つ目は無理なく受け札を採用できる点です。環境トップの2つが純粋にシールドを攻撃してこないデッキだからと言っても、大会にはアグレッシブに攻撃してくるデッキは必ずいます。そこで、受け札が「G・ストライク」しかないといったデッキはなるべく避けたいと考えていて、<同期の妖精|ド浮きの動悸>や<修羅の死神フミシュナ|「この先は修羅の道ぞ」>のような、ついでに「S・トリガー」を持っているカードや「S・トリガー」に頼らずとも手札から<裏斬隠 テンサイ・ハート>を「ウラ・ニンジャ・ストライク」で打点を止めることができます。 この3つの主張点がある上で自分が使い慣れていることも含めて今回のGPは「青黒コンプ」で参加することを決めました。
デッキリスト
青黒コンプ
クリーチャー
計28枚
採用カード解説
異端流し オニカマス
主な使い方は「青単サイバー」の<昇カオスマントラ>で出てきたクリーチャーを手札に戻すのと、「闇王ゼーロ」の墓地から出てくる<DARK MEMORY CONTAINER>を手札に戻すために使います。似たような役割のカードとして<洗打の妖精>や<飛ベル津バサ「曲通風」>がありますが、<洗打の妖精>は相手のマナが溜まってしまうと有効にならない点、<飛ベル津バサ「曲通風」>は「青単サイバー」には有効ですが「闇王ゼーロ」に対して無力な点があり不採用になりました。そして、<異端流し オニカマス>の最も評価した点は、相手から選ばれない能力のおかげでとても場持ちが良いことです。<異端流し オニカマス>を越える手段がどのデッキも要求値が高く、デッキ構築の次点である程度工夫されていない限り多くのターンを稼ぐことができるので、その間にハンデスやメタカードを重ねていくことができます。
ボン・キゴマイム|やせ蛙 ラッキーナンバー ここにあり
主なメタ対象は「青単サイバー」の<愛銀河マーキュリー・スターフォージ>です。<愛銀河マーキュリー・スターフォージ>が自由に動ける状態で場に出てくると、手に負えない状態になってしまうので、仮に場に出てきたとしても動けなくすることが非常に重要になってきます。そして、相手は<愛銀河マーキュリー・スターフォージ>を場に出すために手札を3枚失っていますので<奇天烈 シャッフ>や2枚目の<ボン・キゴマイム|やせ蛙 ラッキーナンバー ここにあり>で続けて<愛銀河マーキュリー・スターフォージ>を止め続けることで、相手の動きを大幅に止めることが可能になっています。その間に相手とのリソースや盤面の数で差を広げていきながら、ビートを仕掛けていき勝利を目指します。冥土人形ヴァミリア・バレル / 修羅の死神フミシュナ|「この先は修羅の道ぞ」
このデッキのハンデス枠です。GP前の環境ではハンデスデッキがいなかったので、相手のハンデス対するガードが緩くなっていたおかげでかなりハンデスの通りが良い環境であったと言えます。<冥土人形ヴァミリア・バレル>は盤面除去とハンデスの両方を同時に行える上に「ハイパー化」することで相手は手札を増やすのが非常に困難になり、リソース回復を咎められる点が非常に優秀です。
<修羅の死神フミシュナ|「この先は修羅の道ぞ」>は数少ない自分の手札を増やすことができるカードです。ハンデスをして自分が1ドローできるので自分の手札を減らさずに相手の手札を1枚減らすことができます。そして、<修羅の死神フミシュナ|「この先は修羅の道ぞ」>が場にいる状態でさらにハンデスをすることでさらに1ドローできるので、さらに相手とのリソース差を広げることが可能です。
奇天烈 シャッフ
「青単サイバー」の<愛銀河マーキュリー・スターフォージ>のような<ボン・キゴマイム|やせ蛙 ラッキーナンバー ここにあり>で止めたクリーチャーを止め続けたり、「闇王ゼーロ」のような呪文を使ってゲームを作る相手に動きを妨害するために採用しました。相手の打点を止めるのが主な役割になるのであれば2~3枚の採用でも十分なのですが、環境に「闇王ゼーロ」がいることによって、必ず<奇天烈 シャッフ>をプレイしたい事やハンドキープ・マナ埋めの難易度を下げるために4枚フルで採用しました。<DARK MATERIAL COMPLEX>が殿堂入りしてから早い段階でビートを仕掛けることが多くなったこともあり、デッキとの親和性が非常に高いため、4枚採用はかなりの好感触でした。
飛翔龍 5000VT
私が「青黒コンプ」に目を付けた追加の要因がこの<飛翔龍 5000VT>を上手く扱えるデッキであるという点です。「青単サイバー」と「闇王ゼーロ」に対して<飛翔龍 5000VT>を召喚すると、相手はできることが非常に限られてしまいます。「青単サイバー」はループによるフィニッシュができなくなるのでゲームを決めるにはビートするしかなくなるのですが、そうなると<裏斬隠 テンサイ・ハート>1枚で全ての打点を止めることができるようになります。「闇王ゼーロ」は盤面が一気に減り<闇王ゼーロ>が使いにくくなる上に仮に使えたとしても、大型クリーチャーが1体出てくるだけなので大幅に行動を制限することが可能です。
こうして「青単サイバー」と「闇王ゼーロ」相手には<飛翔龍 5000VT>を召喚すると相手は次のターン基本的に何もできなくなるので、実質的なトリガーケアができ安全に盾を詰めることができます。
裏斬隠 テンサイ・ハート
主に「青単サイバー」と「トリーヴァバンデ」を意識して採用しました。「青単サイバー」にはメタクリーチャーやハンデスでループを咎めてビートプランに誘導します。そして相手がビートプランを取ってきた時に手札から「ウラ・ニンジャストライク」で<裏斬隠 テンサイ・ハート>を使ってコスト5のカードを切ることで、相手の打点を大幅に減らしてリーサルを阻止することができます。
「トリーヴァバンデ」は<俳句爵 Drache der'Bande>を何度もアンタップさせてワンショットキルを狙ってくるので、<裏斬隠 テンサイ・ハート>でコスト3のカードを切ることで<俳句爵 Drache der'Bande>を止めます。<俳句爵 Drache der'Bande>はブロックされず「G-NEO進化クリーチャー」なので除去耐性があったり、<同期の妖精|ド浮きの動悸>で選べないような状態でリーサルを狙うデッキですので、「S・トリガー」による対処が難しく<裏斬隠 テンサイ・ハート>の採用が非常にポイントになる為、しっかりと3枚採用することにしました。
超暴淵 ボウダン=ロウ
デッキリストを見た時に気が付いた方もいらっしゃると思うのですが、「青黒コンプ」と言いながらこのデッキに<DARK MATERIAL COMPLEX>は採用されておりません。<超暴淵 ボウダン=ロウ>が元々<DARK MATERIAL COMPLEX>だった枠で入れ替えた形になるのですが、なぜ<超暴淵 ボウダン=ロウ>と入れ替えたのかというと、<DARK MATERIAL COMPLEX>を引いて使うのが最初の1~2ターン目しかないからです。基本的に「青黒コンプ」はマナカーブ通りに動くのが理想なので、2・3・4・5ターン目まではコスト通りにカードをプレイしていきます。そうなると<DARK MATERIAL COMPLEX>を出すタイミングが無かったり、仮に<DARK MATERIAL COMPLEX>を出したとしても下に8枚溜まりそうにない。といった状況であることがほとんどでした。ですので、ゲーム序盤にしか使うことのない<DARK MATERIAL COMPLEX>は不採用にして、ゲーム中盤以降であればいつ引いても強い<超暴淵 ボウダン=ロウ>を採用しました。
デッキの回し方
まずは「青黒コンプ」のデッキコンセプトについてですが、「青黒コンプ」はハンデスや盤面除去もできるのでコントロールデッキだと思いがちですが、基本的にはメタビートだと思ってプレイしていった方が勝ちやすいです。大まかなゲームプランは、メタクリーチャーやハンデス・除去を用いて相手に返されないようにしながらじわじわと盾を詰めていくデッキです。基本的にマナカーブ通りにカードをプレイしていくのですが、マナカーブ通りに動くことが理想であるからこそ序盤のマナ埋めがかなり重要になってきます。特に黒マナを1枚でもいいので準備出来るかどうかが重要です。デッキ内の闇のカードが合計17枚でその内8枚が多色、そして〈アーテル・ゴルギーニ〉は5ターン目に最優先でプレイしたいカードなのでなるべく手札にキープしたいです。ですので、<冥土人形ヴァミリア・バレル>や<修羅の死神フミシュナ|「この先は修羅の道ぞ」>が手札にある時はなるべく1ターン目にマナチャージしておくことで手札に多色が嵩張るのを避けつつ黒マナを用意することができます。 次にプレイするカードについてですが、相手のマナチャージをよく観察してどのようなデッキタイプであるかを予想しながらプレイしていきます。踏み倒しを多用してきそうなら<異端流し オニカマス>を優先して召喚しますが、踏み倒しをしそうにない場合や序盤からビート仕掛ける必要もないのであれば何も出さないことも一つの手です。なぜかというと、「青黒コンプ」は基本的に手札を増やす手段が無いのでクリーチャーを出さずに手札の枚数をキープことも重要になってきます。しかし、相手が沢山ドローするデッキなのであればとりあえず2ターン目にクリーチャーを出した後に<冥土人形ヴァミリア・バレル>を召喚して「ハイパー化」することで相手にドローをさせなくすることができます。
そして、メタカードが有効な相手には<ボン・キゴマイム|やせ蛙 ラッキーナンバー ここにあり>や<奇天烈 シャッフ>で相手の動きを妨害し、逆にメタカードが有効ではない相手や相手のデッキタイプが読めない場合はハンデスで相手の動きを妨害します。 こうしてメタカードやハンデスで相手が思うように動けない隙に少しずつ相手のシールドを減らして数ターン掛けてダイレクトアタックを目指していきます。
最後に
いかがでしたでしょうか。「青黒コンプ」は序盤からビートを仕掛けていくのか、ハンデスや盤面除去でコントロールしていくのか、自分の手札や相手のデッキに合わせてどんなプレイを取るのか変わって試合ごとにプレイを考えるのが非常に面白いデッキです。
メタカードや受け札など、かなり自由に組み替えることができるデッキですので、今回ご紹介したデッキリストを元に環境に合わせて採用カードを入れ替えて遊んでみてください!
ここまで読んでいただきありがとうございました。